「建築施工管理技士を取りたいけど、2級を受けずにいきなり1級を目指しても大丈夫?」
そう疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、私自身が2級を経ずに1級に一発合格した体験をもとに、「いきなり1級って実際どうなのか?」をわかりやすく解説します。
結論から言えば、一定の条件と進め方を理解していれば、いきなり1級は十分に狙えます。
ただし、誰にでもおすすめできるわけではないので、自分の経験・目的に合っているかどうかも一緒にチェックしていきましょう。
建築施工管理技士とは?1級と2級の違い
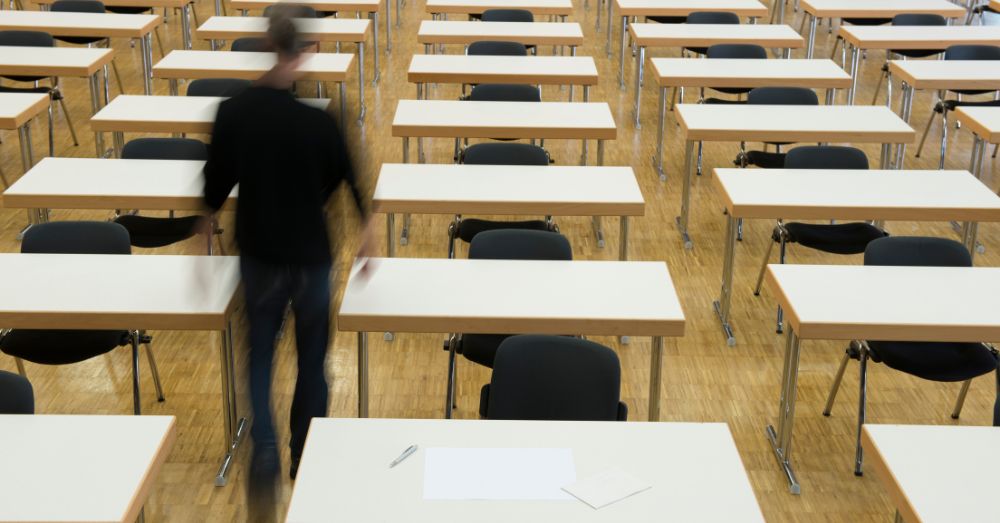
建築施工管理技士は、建築工事における施工計画・安全管理・工程管理などを担う技術者に必要な国家資格です。
1級と2級の違いは大きく分けて以下の3点です。
- 対応できる工事の規模
2級は主に中小規模の建築工事、1級は大規模建築物や官公庁工事なども担当可能 - 実務上の権限
1級を取得すると「主任技術者」や「監理技術者」として現場責任者になれる機会が増える - 転職・年収への影響
1級保持者は企業からの評価も高く、年収アップや昇進の条件になることも
「どうせ取るなら1級まで」と考える方が多いのも、こうした理由からです。
【体験談】2級を飛ばして1級に合格したときの実際の勉強方法

私は2019年に、2級を経ずに1級建築施工管理技士試験に一発合格しました。
当時、インフラ系企業にて建築技術者として勤務し、現場監理などを担当していました。
合格の決めてとなったと感じたポイントは3つ!
- 過去問をベースに勉強する
- 二次試験の経験記述問題は、合格者から添削してもらい「視点」が誤っていないかチェックを受ける
- 模試を受ける
私が合格のために行った主な具体的な対策は以下の通りです!
一次試験(学科)対策
過去問を中心に繰り返し解くことを徹底。
テキストもありましたが、ほとんど読まず、過去問集のみで乗り切りました。
毎朝1時間、習慣化して勉強することで、無理なく継続できました。
二次試験(実地)対策
頻出の記述問題をノートにまとめ、赤シートで隠して暗記&アウトプットを反復。
記述の構成力が求められるため、模試(総合資格学院)で添削を受け、書き方の改善に役立てました。
記述添削は、独学では得られない「第三者目線」での指導を受けられる点で非常に効果的でした。
1級建築施工管理技士の受験資格。旧制度との違いと技士補の位置づけも解説

1級建築施工管理技士の受験制度は、2024年度(令和6年度)から大幅に改正されました。
特に注目すべきは、第一次検定(学科試験)の受験要件の緩和と、「施工管理技士補」という新たな肩書きの誕生です。
ここでは、新旧制度の違いを踏まえながら、どの段階で何が必要なのかをわかりやすく解説します。
第一次検定(学科試験)の受験資格
| 項目 | 旧制度 | 新制度(令和6年度〜) |
|---|---|---|
| 受験資格 | 学歴+実務経験が必要 | 満19歳以上なら誰でも受験可能 |
| 学歴制限 | 高卒・高専・大卒などで実務年数が異なる | なし(学歴・実務不問) |
| 実務経験 | 必須 | 不要 |
| メリット | 実務経験が豊富な人に有利 | 未経験者でもチャレンジできる |
学科試験は誰でも受験可能になり、ハードルが大きく下がりました。
第二次検定(実地試験)の受験資格
実地試験は、「施工管理の実務経験があること」が前提条件です。
合格するには、実際に現場で管理業務を行った経験を証明できなければなりません。
以下のいずれかに該当していれば、第二次検定(実地)を受験できます。
- 特定実務経験を1年以上含む3年以上の実務経験
- 監理技術者補佐の経験が1年以上
- または、旧制度に基づいた学歴+実務経験年数(※経過措置あり)
実地試験は今も「経験重視」の試験であり、未経験者がすぐに受けられるわけではありません。
詳細は、国土交通省の改定案内も参考にしてみてください!
技士補とは?第一次検定合格者に与えられる新しい肩書き
令和6年度から、第一次検定(学科)に合格すると「施工管理技士補」の資格が付与されるようになりました。
「技士補」は、監理技術者や主任技術者の指導を受けながら現場に関わる補佐的な立場です。
技士補の主な特徴
- 名刺や履歴書に「施工管理技士補」と記載できる
- 現場での実務経験としてカウントされるケースもあり
- 第二次検定の受験要件(特定実務経験など)を満たすルートとして機能する
「すぐに施工管理技士になれない」期間でも、公式な肩書きで現場経験を積めるのが大きなメリットです。

でも、既に実務経験を積んでいて、いきなり1級の施工管理技士として活躍したいと考えている人もいるはず。
次の章では、受験前に押さえておきたい3つのポイントを解説します。
制度改正で変わった!受験前に押さえておきたい3つのポイント
改正によって受験チャンスが広がる一方で、注意しておきたい点もあります。
以下の3点は特に重要です。
ポイント①:学科試験は誰でも受けられるが、合格後すぐに実務者になれるわけではない
学科合格=資格取得ではありません。
合格後に「技士補」として実務経験を積み、あらためて実地試験に合格する必要があります。
ポイント②:実地試験には実務経験の“中身”が問われる
ただの作業補助ではなく、施工計画・工程管理・安全管理など、責任ある立場での経験が必要です。
「自分は補助だけだった」という場合は、経験の内容を明確にできるよう整理しておきましょう。
ポイント③:旧制度・新制度どちらでも申請できる(経過措置あり)
令和10年度までは、従来の「学歴+実務年数」による受験も認められています。
すでに実務経験が豊富な方は、旧制度のほうが有利になる場合もあります。
いきなり1級を目指すメリット・デメリット


いきなり1級にチャレンジすることには、当然ながら良い点もあれば注意すべき点もあります。
ここでは、私の経験も踏まえて、そのメリット・デメリットを整理してみます。
メリット
1. 時間と費用を節約できる
2級を経由せずに1級に直接挑戦することで、受験にかかる時間も費用も一度分で済みます。
資格スクールや参考書の購入費も1回分で済むため、トータルコストを抑えられるのは大きな利点です。
2. キャリアアップが早まる
1級を取得すれば、大規模工事の現場や監理技術者としての役割を任される可能性も高くなります。
結果的に、昇進や転職にも有利に働き、年収アップにもつながりやすくなります。
3. 社内外での信頼度が高い
「1級建築施工管理技士」という肩書きは、技術者としての信頼度や安心感を与える要素でもあります。
特に建設業界では、資格の有無がそのまま実力の証明になる場面も多いため、武器になります。
デメリット
1. 難易度が高い
1級は2級よりも試験範囲が広く、問題のレベルも高めです。
独学で取り組む場合は、特に計画的な勉強と強いモチベーションが必要になります。
2. 二次試験の記述がハードルになりやすい
記述式では、実務経験をもとに論理的に説明する力が求められます。
現場での経験が浅い場合、実例が書けずにつまずくケースも少なくありません。
3. 不合格の場合のダメージが大きい
1級一本に絞って受験し、不合格だった場合、次回まで1年待たなければなりません。
受験期間が長引くことで、モチベーションが下がることもあります。
いきなり1級を目指す際の注意点
「いきなり1級」は、たしかに効率の良い選択肢ですが、誰にとってもベストな道というわけではありません。
ここでは、実際に目指すうえで気をつけておきたいポイントをまとめます。
1. 受験資格を正確に確認しよう
まず前提として、受験資格を満たしていなければ挑戦自体ができません。
学歴と実務経験の組み合わせによって細かく条件が異なるため、公式の案内をしっかり確認しましょう。
実務経験の証明書類の提出も必要なので、在籍企業で証明してもらえるかどうかの確認も早めに行っておくと安心です。
2. 実務経験を「言葉で説明できる」力が必要
特に二次試験の記述対策では、「実務経験がある」だけでなく、それを正しく言語化して書けるかが重要になります。
施工計画・工程管理・安全管理など、自分の関わった事例を具体的に整理しておくことが合格への近道です。
3. 独学が不安なら、早めに対策講座を検討
完全に独学で進める場合、情報の取捨選択や勉強の優先順位を自分で判断する必要があります。
もし迷いが多いようなら、早めに模試や通信講座を利用するのも有効です。
特に記述添削は、独学では得られない視点を補ってくれるので、合格率を上げるための一助になります。
4. 「合格までにかけられる時間」と「生活のバランス」を見極める
仕事が忙しい中での受験勉強は、体力・気力ともに消耗します。
無理な計画を立てると途中で挫折しやすいため、「毎日1時間だけでも継続できるか」など、自分の生活スタイルと向き合ったうえで無理のない学習設計をしましょう。
いきなり1級を目指すべき人の特徴


以下のような方は、いきなり1級を目指しても現実的に合格可能です。
- 学歴と実務経験の要件を満たしている
- 現場での実務経験があり、記述に落とし込める実績をもっている
- 毎日コツコツと勉強できるタイプ
- 2級を経由する時間・費用を最小限にしたい方
逆に、まだ実務経験が浅い、あるいは資格試験自体が初めてという方は、まずは2級で試験慣れするのも選択肢です。
独学が不安な人におすすめの講座・教材


私自身は独学で合格しましたが、実際には「何から手をつけていいかわからない」「記述対策が苦手」という声も多く聞きます。
そうした方には、信頼できる通信講座や模試の活用がおすすめです。
通信講座・模試の比較表(独学が不安な方におすすめ)
| 講座名 | 特徴 | 向いている人 | 添削指導 | スマホ対応 | 価格帯(目安) |
|---|---|---|---|---|---|
| SAT講座 | 映像講義中心で理解しやすい | スキマ時間に効率的に学習したい人 | ◎ | ◎ | 税込38,280円~ |
| 独学サポート事務局 | 添削指導が充実 | 文章力に自信がない人 | ◎ 別料金で作文作成代行もあり | ×(紙中心) | 税込10,100円~ |
| CIC(日本建設情報センター) | Web講座・DVD講座・通学講座の3つのタイプが選べる | 教材をしぼって、集中的に合格を目指したい人 | ◎ | ◎ | 税込33,000円~ |
※価格や内容は時期・プランによって変動する可能性があります。詳細は各公式サイトをご確認ください。
表で見てわかるように、それぞれに強みがあります。
独学が不安な方は、こういったサポートをうまく活用しながら、自分に合った学習スタイルで進めてみてください。
また、私のように、基本的には独学で、模試だけ受ける、経験記述の添削だけ受けるやり方もおすすめです。
現場・技術系を専門とする通信講座学校のSATでは、無料の資料請求も実施しています。
今なら以下のプレゼントが送られてきます!
①最短合格法特別動画
【動画内容】
施工管理技士試験はパターンが決まっている
何をどのぐらい学習すれば合格できるか?
数値系 / 大小・長短系 / 入替比較系 / 計算系
②各講座のサンプルテキスト
③期間限定1分でも短い勉強時間で資格試験にパスしたい方向けの1冊
\/
まとめ


いきなり1級を目指すのは、決して「無謀」ではありません。
条件さえクリアできていれば、十分に合格は狙えます。
私自身も2級を取らずに1級を独学で一発合格できました。
ただし、独学はしっかり計画を立てて勉強しないと途中で挫折しがちです。
「自分にとっての最短ルートは何か?」をよく考えたうえで、1級にチャレンジしてみてください。

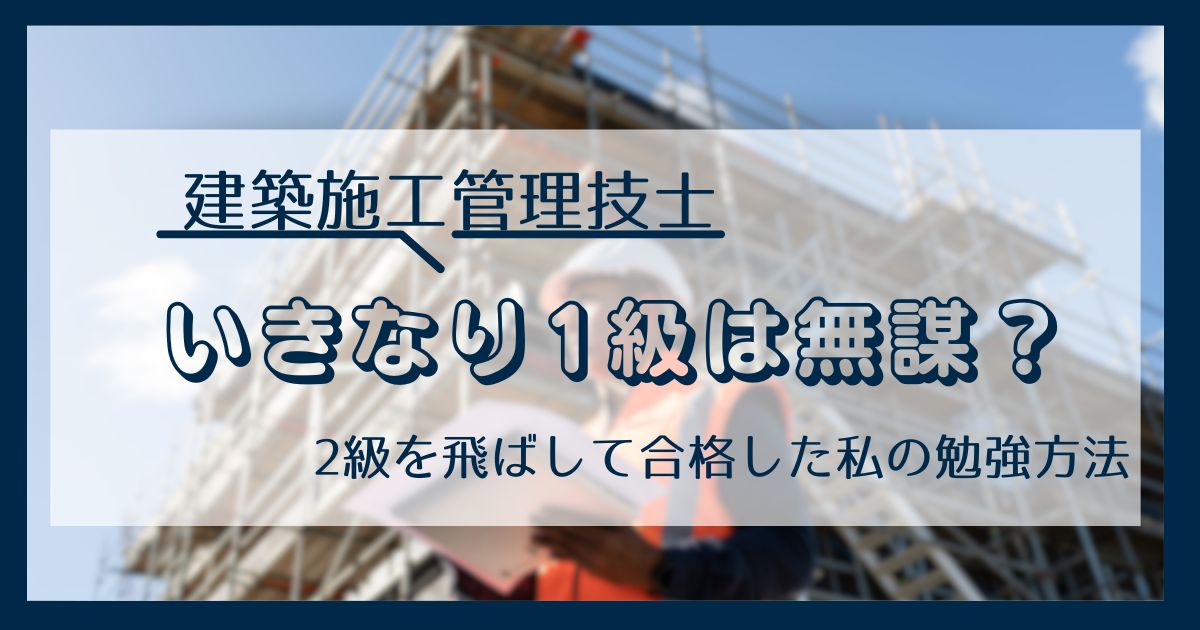
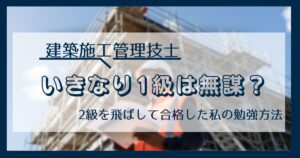
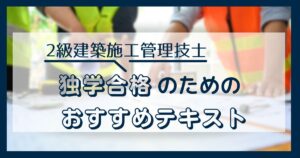
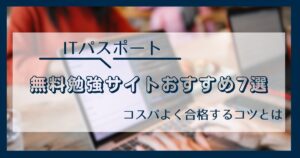

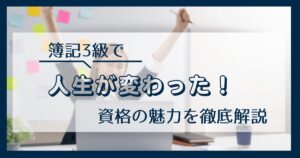
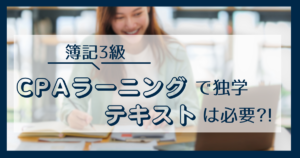
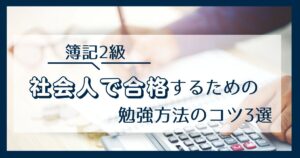
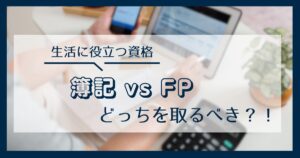
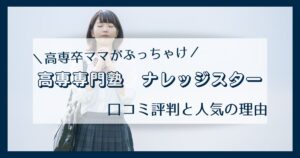
コメント